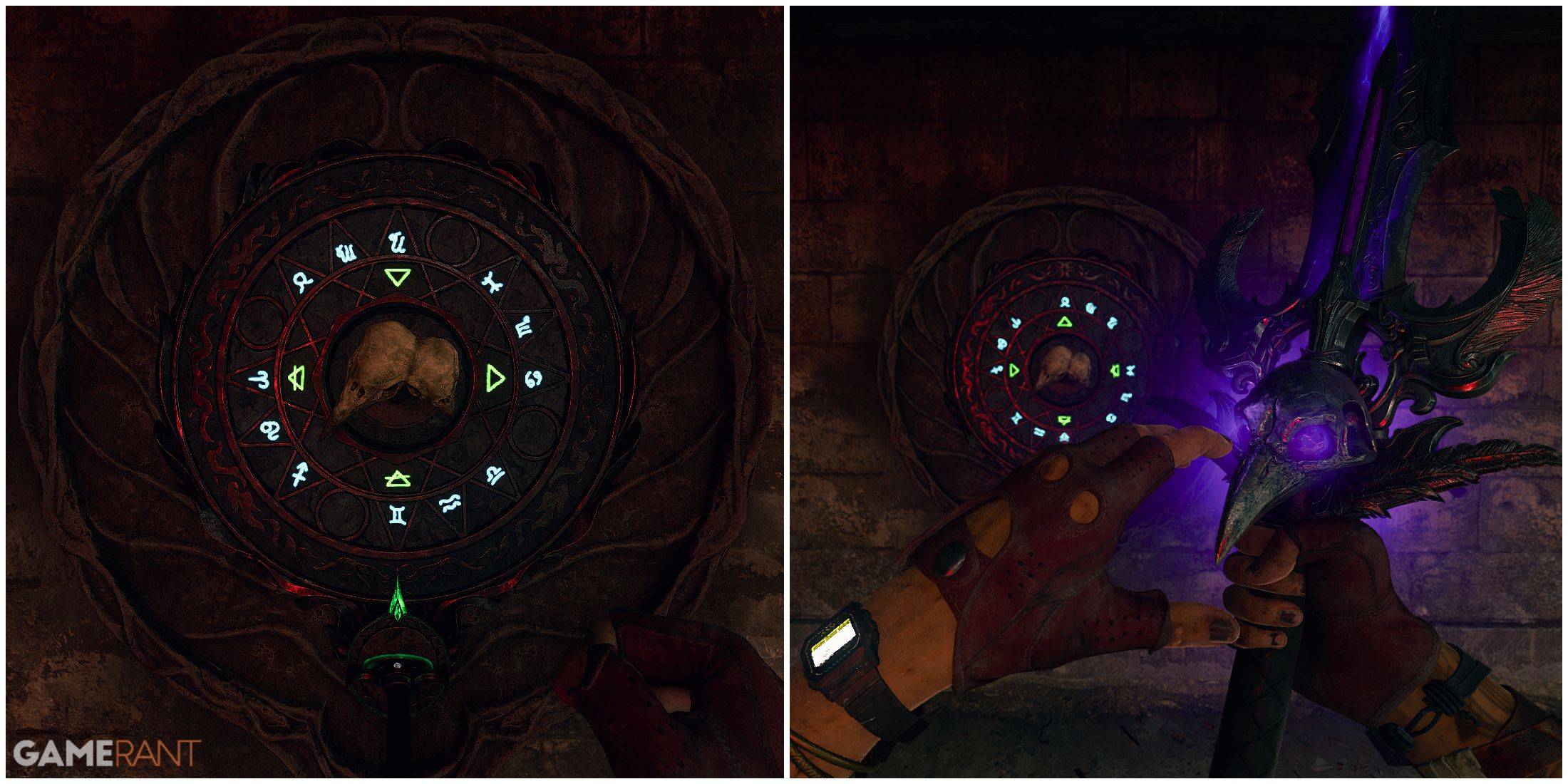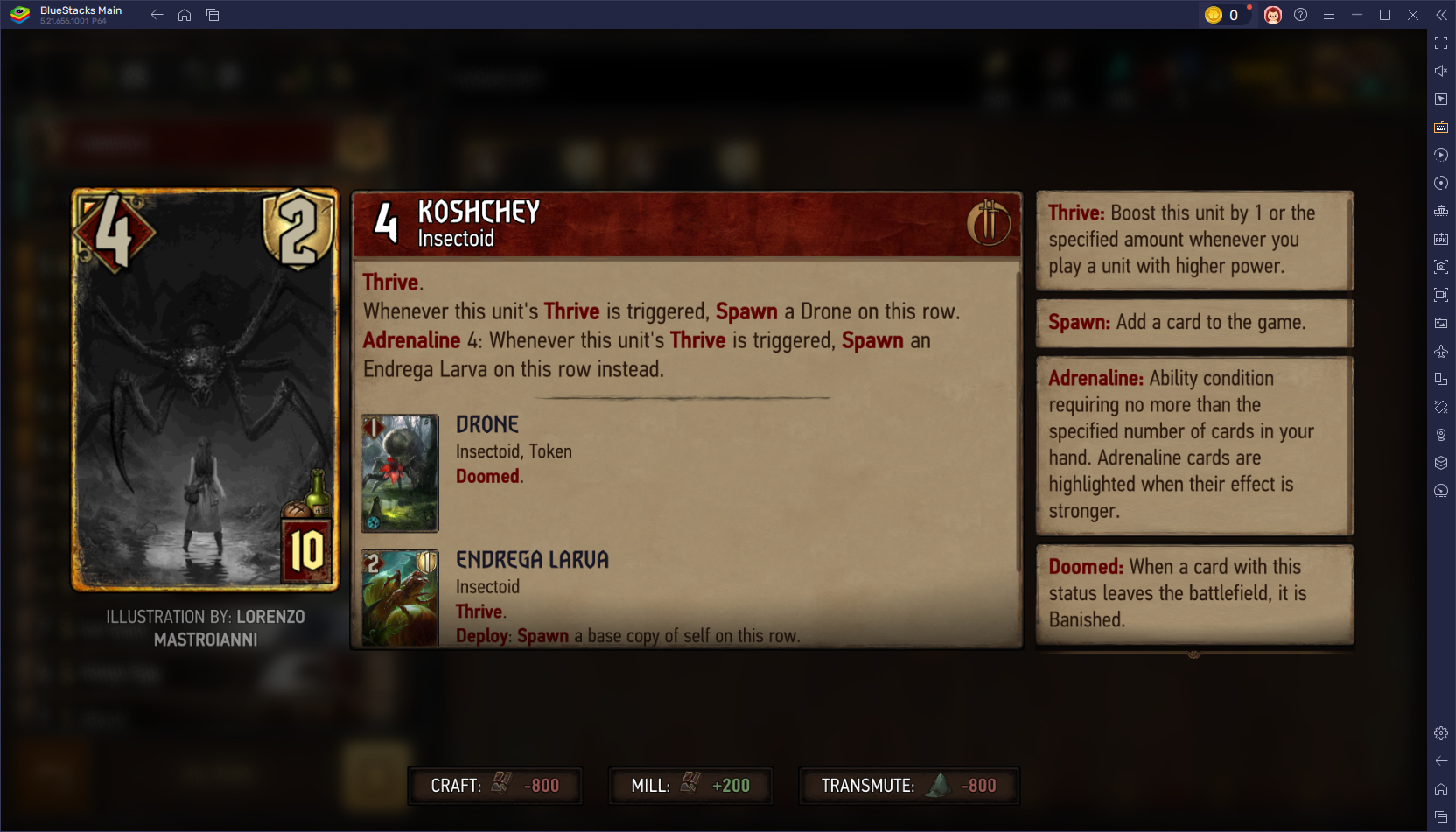「アサシン クリード II & III」の脚本の頂点
- By Samuel
- Sep 29,2025
『アサシン クリード』サーガで最も忘れがたい瞬間の一つは、シリーズ第3作『アサシン クリード III』序盤に訪れる。ヘイザム・ケンウェイが新天地で仲間を集める場面だ。プレイヤーは当初、これがアサシンたちの集団だと信じ込む——隠し刃を操り、エツィオ・アウディトーレのようなカリスマを放ち、ネイティブアメリカンを解放しイギリス兵を屈服させる英雄的振る舞いをするヘイザム。衝撃的な真実が明かされるのは、彼がテンプル騎士団の信条「理解の父の導きあらんことを」を口にした瞬間だ。そこではじめて、私たちがシリーズを通して敵対してきた陣営を助けていたと気付く。
この見事な仕掛けは『アサシン クリード』の真髄を体現している。初代作品が「ターゲット狩り」という魅力的なコンセプトを導入した一方、キャラクター描写は浅かった。『アサシン クリード II』で忘れ難いエツィオが登場したものの、チェーザレ・ボルジアなどの敵役は未発達だった。ユービーアイソフトが狩る側と狩られる側の双方に等しく力を注いだのは『アサシン クリード III』が初めてであり、後の作品が追従できない物語とゲームプレイの調和を達成した。

RPG化した近年作は評論家からの評価が高いが、多くのファンはシリーズが長年衰退していると指摘する。原因については議論が分かれる——神々との神話的戦いを批判する声もあれば、史実人物が虚構の主人公を置き換えることに反対する意見もある。しかし核心的な問題はもっと深いところにある。膨張しすぎたオープンワールドの影で、キャラクター駆動型のストーリーテリングが徐々に蝕まれているのだ。
ダイアログツリー、XPシステム、マイクロトランザクションといったRPGメカニクスへの移行は、広大だが空虚な体験を生んでいる。サブコンテンツは繰り返し感が強く、メインストーリーも過去作のような磨きがかけられていない。『オデッセイ』のような作品は『AC2』よりコンテンツ量が多いが、その多くが人工的で説得力を欠いている。
没入感を理論上高めるプレイヤーの選択肢は、しばしば逆効果だ。多岐にわたる分岐ダイアログは、過去作の緊密に脚本化された物語と比べ洗練度が落ちる。アクションアドベンチャー時代の焦点を絞ったアプローチこそ、プレイヤーの好みに合わせる必要なく繊細なキャラクター描写を可能にしていた。
『オデッセイ』のコンテンツは往々にして無機質で——NPCが明らかにプログラムされた存在のように振る舞い、没入感を損なう。これはPS3時代の卓抜した脚本——エツィオの情熱的な演説や、ヘイザムが息子コナーに放つ最後の冷酷な言葉——
「涙を流して過ちを認めると思うな。お前はとっくに殺すべきだった」

現代の作品ではアサシンとテンプルの対立も単純化されている。過去作は道徳的グレーゾーンを探究した——『AC3』で瀕死のテンプル騎士ウィリアム・ジョンソンは先住民虐殺を防べたと主張し、トーマス・ヒッキーはアサシンの理想主義を嘲笑い、ベンジャミン・チャーチは対立を単なる「視点の差」と断じる。ヘイザムはワシントン将軍がコナーの村を焼き払うよう命じた事実を暴き、プレイヤーに全てを疑わせる。
「エツィオズ・ファミリー」の根強い人気はこの違いを物語っている——この楽曲が捉えたのは単なる歴史的背景ではなく、個人の悲劇だ。現代の作品には圧倒的なスケールとグラフィックがあるが、ユービーアイソフトにはシリーズ絶頂期を定義した焦点の定まったストーリーテリングを取り戻してほしい。残念ながら、終わりなきコンテンツとライブサービス要素に囚われた業界では、こうした親密な物語はもはや商業的に成立しえないのかもしれない。
最新ニュース
もっと >-

- ラブ、デス+ロボッツ シーズン4:知性を持つおもちゃが恐竜と赤ちゃんに加わる
- Dec 14,2025
-

- 『モータルコンバット1』でバーバリアンコナンのゲームプレイ映像を初公開
- Dec 13,2025
-
- Star Wars Outlaws Coming to Nintendo Switch 2
- Dec 13,2025
-
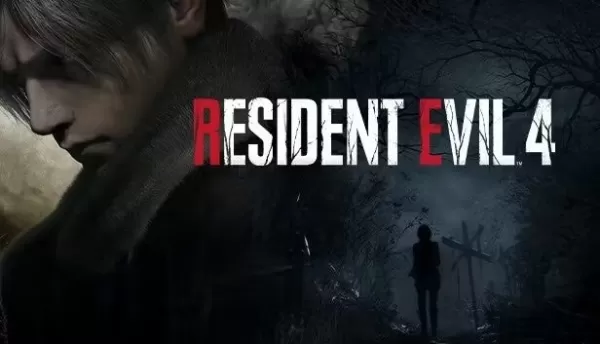
- カプコンセール:『バイオハザード4 リメイク』『ドラゴンズドグマ2』のお得な情報
- Dec 12,2025
-

- ソニーWH-1000XM6 ヘッドフォン、購入可能に
- Dec 12,2025